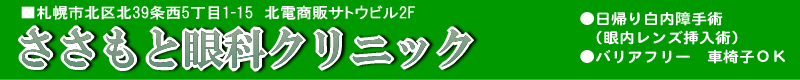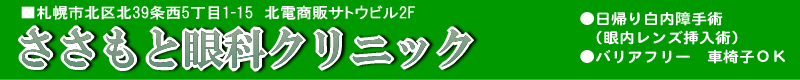|
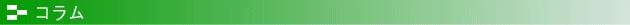 |
| |
| 院長コラム 〜視界良好〜 |
| 目次 |
| ・・・こんな飛蚊症が危ない |
(第1回) |
| ・・・眼底出血ってどんな病気? |
(第2回) |
| ・・・進化した白内障手術 |
(第3回) |
| ・・・カゼ薬と緑内障 |
(第4回) |
| ・・・忍びよる糖尿病網膜症 |
(第5回) |
| ・・・40歳は老眼の始まり |
(第6回) |
| ・・・コンタクトレンズあれこれ |
(第7回) |
| ・・・加齢黄斑変性ってなに? |
(第8回) |
| ・・・冬につらいドライアイ |
(第9回) |
| ・・・北海道のアレルギー性結膜炎 |
(第10回) |
| ・・・早期発見で治る網膜剥離 |
(第11回) |
| ・・・日帰り手術と白内障手術 |
(最終回) |
| |
|
| |
| 院長コラム 〜目からウロコ・目の病気〜 |
| 目次 |
| ・・・飛蚊症 |
(第1回) |
| ・・・白内障 |
(第2回) |
| ・・・緑内障 |
(第3回) |
|
・・・はやり目 |
(第4回) |
|
・・・加齢黄斑変性 |
(第5回) |
|
・・・コンタクトレンズの合併症 |
(第6回) |
電話
|
・・・ぶどう膜炎 |
(第7回) |
| 011-700-6661 |
・・・アレルギー性結膜炎 |
(第8回) |
|
・・・糖尿病網膜症 |
(第9回) |
|
・・・ドライアイ |
(第10回) |
|
・・・複視 |
(第11回) |
|
・・・眼底出血 |
(第12回) |
|
・・・赤ちゃんの目の病気 |
(第13回) |
|
・・・老眼 |
(第14回) |
|
・・・網膜剥離 |
(最終回) |
|
|
|
|
|
|
|
こんな飛蚊症があぶない (第1回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
飛蚊症(ひぶんしょう)という言葉を開いたことがあると思います。白い雪の上や真っ白な壁をみた時に、虫が飛んで見えたり、ごみが飛んで見えたりする症状を指します。よく見てみると、目の動きにつれて、ゆっくりと流れるように動いています。いつも同じ場所に見えるわけではなく、体の向きによっても変化します。日常生活や暗い時は気がつきませんが、明るいところ、特に白い壁が背景の時にはっきり見えます。
光は眼球の角膜と水晶体を通って網膜に届きます。水晶体と網膜の間に硝子体(しょうしたい)という透明でゼリーのようなものがあります。この硝子体に濁りがあると、その影が網膜に映り飛蚊症となります。飛んで見える形はさまざまで虫状、ゴマ状、糸状、輪状と訴える人が多く、時にはカエルの卵状と形容する人もいます。
飛蚊症には、生理的なものと病的なものがあります。生理的なものは、生まれつきのものや加齢によるもので、どんな人にも出現します。若年者では小型の黒点や糸状の濁りを視野の中央に自覚することが多く、生理的に液化した硝子体の混濁が原因です。子供のころの硝子体は動きませんが、年齢が上がってくると網膜に近い部分の硝子体が液化して硝子体ポケットが形成されて濁りが出てきます。これが若年者の生理的飛蚊症です。
高齢者では、突然、大きな輪状の濁りが視野の中央からやや耳側に見えることがあります。これは加齢で硝子体が網膜から剥離した時に見られます。生理的飛蚊症は基本的に加齢が原因ですから、消えてなくなることはありません。
ところが、一度にたくさんの濁りが見えたり、濁りの数がどんどん増えたり、全体にかすんで見えるときは生理的な飛蚊症ではなく、危ない飛蚊症すなわち病的な飛蚊症の可能性があります。加齢による硝子体剥離がおきる時に、硝子体と網膜の間に癒着があれば、そこの網膜が裂けて網膜剥離や硝子体出血を起こします。加齢だけでなく、糖尿病網膜症や綱膜静脈閉塞症の新生血管から硝子体中に出血すると飛蚊症を起こします。ぶどう膜炎や眼内炎などでもかすみが出現します。網膜剥離は急いで光凝固治療や入院して手術治療が必要です。病的な飛蚊症では原因疾患をよく調べて、適切な治療を受けなくてはいけません。飛蚊症を自覚したら、眼科で眼底検査を受けて、生理的なものか、病的なものか診断してもらうことが大切です。
|
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
眼底出血ってどんな病気? (第2回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
眼底出血という言葉を聞いたことがあると思います。知り合いや家族の中に、眼科で眼底出血があると言われた、という人がいるかもしれません。眼底出血は、文字通り眼の眼底に出血を認める状態を指します。眼底出血を起こす病気はいろいろあって、眼の血管の病気、糖尿病、炎症、外傷などがあります。その中で、眼の血管の病気と糖尿病が、眼底出血を起こす疾患の代表です。今回は、眼の血管の病気、その中でも網膜静脈閉塞症についてお話します。
体の血管が詰まる(=閉塞する)病気は、脳梗塞や心筋梗塞が有名です。どちらも、動脈という栄養を運ぶ大事な血管が詰まる病気です。では、静脈が詰まるとどうなるでしょうか。体のほとんどの組織では、静脈が閉塞しても別の道(側副路)ができて、血液は普通に流れて出血しません。ところが、眼底の血管は網膜という非常に薄い膜の中を走っていて、網膜静脈が閉塞してしまうと、他の道ができる余裕がなくなり、動脈から流れてくる血液があふれて出血するのです。
眼以外の動脈と静脈は別々のところを走っていますが、網膜はとっても薄いために、網膜動脈と網膜静脈はところどころで密着(交叉)しています。密着したところでは、動脈と静脈が外膜を共有しています。動脈は高血庄や高脂血症ですぐに固くなります。固くなった動脈は、静脈を押しつぶしてしまいます。これが網膜静脈閉塞症です。
眼球の奥で静脈が詰まってしまうと、網膜中心静脈閉塞症になります。網膜の中で枝分かれした静脈が詰まると網膜静脈分枝閉塞症になります。網膜中心静脈閉塞症は、突然、まったく見えなくなりますから、すぐに気付きます。急いで治療すると、視力回復の可能性がありますので、すぐに眼科受診が必要です。
網膜静脈分枝閉塞症は、詰まる血管の場所によって症状が異なります。視力に大事な黄斑部の静脈閉塞では、視力が低下するため早期に気付きます。しかし、黄斑部にかからない静脈閉塞では、なかなか気付きません。片目で見ると、ゆがんで見えたり、視野が欠けたりします。視力に影響がなくても、詰まった静脈のところから、新生血管ができて硝子体出血を起こしたり、網膜が破れて網膜はく離を起こしたりすることがあります。
ときどき、片方の目で交互に見て違いがないかを確かめ、もし、何か異常を感じたら、すぐに眼科専門医の診察を受けることが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
進化した白内障手術 (第3回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
1年間の白内障手術は、日本でおよそ90万件、アメリカでは280万件と言われています。現在の白内障手術の大部分は、小切開白内障手術と折りたたみ式の眼内レンズを挿入する方法が行われています。小切開手術は傷が小さいため治りが早く、手術後早期から快適な生活ができます。これほど広まった白内障手術ですが、現在の手術方法が確立したのは最近のことです。
白内障という病気は大昔からあります。長生きすると誰でも白内障になり、日本では「しろそこひ」と呼んでいました。白内障は水晶体が濁る病気ですから、濁った水晶体を取り出せば視力の回復が期待できます。白内障手術といえば、水晶体を取り出す手術を指しました。水晶体は焦点を合わせる働きがあるので、水晶体がなくなるとピントが全然合わなくて、遠くも近くもぼんやりしてよく見えません。手術後はピントを合わせるため、厚い凸レンズのメガネが必要でした。レンズがあまりにも厚いので、片方だけのメガネではバランスが取れず、白内障の進行を待って必ず両目の手術を行いました。
現在の白内障手術では、濁った水晶体を摘出して、かわりに透明な眼内レンズを目の中に挿入します。これを水晶体再建術といいます。よく考えると、目の中にわざわざ異物を入れるというのは、本来とんでもないことでした。目は、物を見るための大切な器官ですから、異物を入れて炎症が起きれば見えなくなってしまいます。木の枝が目に刺さったり、ハンマーの破片が目に飛び込み失明する例はたくさんあります。ところが、第2次大戦中の英軍パイロットが、風防のガラスが割れて目の中に入り、そのまま何事もなく生活していることがわかりました。目の中にガラス片がはいっても炎症が起きなかったのです。
そこで、多くの研究者が目の中に入っても炎症が起きない透明な材料を探し、レンズの働きをする構造を調べたのです。はじめはガラスを使いましたが、重たくてだめでした。ハードコンタクトレンズに使われる硬い素材が広く使用され、今では、折り曲げて小さな切開創から挿入できる、シリコン素材やアクリル素材が使われます。現在の眼内レンズは、挿入後の生涯にわたって使用が可能です。手術時間も15分から30分程度に短縮され、日帰り手術が可能になり、私のような開業医が多数の手術を行うようになりました。白内障かなと思ったら、眼科専門医にお気軽にご相談ください。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
カゼ薬と緑内障 (第4回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
緑内障という病気を、皆さんご存じでしょう。白内障は手術すれば治るけれど、緑内障は治らないので怖い病気だと聞いているかもしれません。ところで、薬局のカゼ薬や、病院で処方される内服薬の注意書きに、「緑内障の方はご注意ください」「緑内障の疑いのある方は、先生とご相談ください」と、書かれているのを見たことがあると思います。カゼ薬で緑内障が悪化する場合もあるということです。
緑内障の人は、40歳以上では20人に1人といわれています。多くの人が、薬を飲んで見えなくなるのでしょうか。そんなことはありません。カゼ薬で緑内障を悪化させるのは、線内障の一部のタイプに限られます。
眼はピンポン玉のような形をしています。眼の中は、「房水」という水で満たされています。
もし、外傷や病気で失明して、眼の中の房水が減ってしまうと、眼球萎縮になります。反対に、眼の中に房水がたまって、それでも房水が増え続けるとどうなるでしょうか。房水が増えすぎると、眼圧が上がり、硬くなってしまい、少しでも柔らかいところを圧迫します。圧迫されて障害されるところが視神経です。緑内障は、視神経が圧迫されて、見えなくなるわけです。
眼球に過剰に房水がたまるのは、房水の通り道が詰まってしまうからです。カゼ薬などが、緑内障を悪化させるのはどうしてでしょうか。一部の薬は、瞳孔を大きくする働きがあります。瞳孔が大きくなるときに、虹彩が房水の流れを止めてしまうことがあります。房水が流れなくなり、眼圧が急に上昇して、急性緑内障発作になります。急性緑内障発作は、視力低下、強い痛み、充血、瞳孔散大を認め、急いで治療しないと失明する可能性があります。このような緑内障は、緑内障全体の約10%以下であることがわかっています。
日本で一番多い緑内障は、開放隅角緑内障といって瞳孔が大きくなっても、眼圧は上がりません。ほとんどの緑内障では、注意書きのある薬でも大丈夫です。現在、眼科に通院中の方も、薬物治療や手術治療を受けていれば安心です。ただし、ステロイド薬は、どんな人でも眼圧を上げる可能性があるので注意が必要です。では、眼科で診察をまったく受けていない人はどうでしょうか。普段は気にしていないかもしれませんが、緑内障は知らず知らずのうちに進行します。40歳を過ぎたら年1回は、眼科専門医の検査を受け、緑内障の危険性があるか、診察を受けるとよいでしょう。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
忍びよる糖尿病網膜症 (第5回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
わが国では、糖尿病の人は約700万人、糖尿病予備軍も約700万人と言われ、合計すると日本人の10人に1人は糖尿病か糖尿病になりかけの人ということになります。健康診断などで、『糖尿病の気がありますよ』と言われると、ドキッとしますよね。『もう立派な糖尿病です。しっかり食事制限をして運動をしましょう』と診断された方は、必ず眼の検査を受ける必要があります。糖尿病が進むと眼が見えなくなるかもしれないという恐ろしさは、誰もが知っていることと思います。糖尿病の方は、これまでに1回は眼科で眼底検査を受けたことがあると思います。ほとんどの人は、『大丈夫です。眼底出血はありません』と、診断されたことでしょう。
ところが、ここからが重要です。眼科医に、『糖尿病と診断されたので定期的に検査を受けてください』と、言われたはずです。では、きちんと眼底検査を受けていますか?一度大丈夫といわれ、安心してはいませんか?糖尿病の方は、おおらかな性格、糖尿病気質といっても良いかもしれません、大丈夫といわれると、安心してこれからもずっと大丈夫と思いがちです。糖尿病網膜症は、急には進みません。一度、二度と検査を受けて、安心してはいけないのです。
糖尿病網膜症は、ほとんどが10年以上の糖尿病歴の方におきてきます。多くの人は、いつから糖尿病になったかわかりません。糖尿病は、血糖値が高くなり、細い血管が目詰まりしてしまう病気です。網膜にはたくさんの細かい血管があり、血管が詰まると、出血や小さい血管瘤が出たりします。出血があっても視力には影響ありません。網膜症がさらに進んで、硝子体出血や糖尿病黄斑症といった段階にまで進んで、はじめて視力が低下します。直接視力に影響が出る時には、網膜症は失明の一歩手前まで来ているのです。レーザー網膜光凝固治療や入院して手術治療を行っても、失明を防ぐのが精一杯で、元の視力に回復させることは難しいのです。
糖尿病と診断されたら、必ず1年に1回は眼科専門医の検査を受けてください。眼底出血がありますよ、といわれた方は少なくとも3カ月に1回の診察が必要です。視力が下がったり、硝子体出血の方は2週間から1カ月に1回は受診しましょう。最後の眼科受診から足が遠のいた方も、もう一度診察を受けましょう。眼科専門医であれば、受診間隔が空いてしまった人にも、必ず優しく対応してくれるはずです。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
40歳は老眼の始まり (第6回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
人間の目は、カメラのオートフォーカスと同じように、遠くにも近くにも自動的にピントが合うようにできています。 視力の良い人は、遠くの看板も、手元の新聞や文庫本も、メガネなしで読んでいることと思います。 また、近視の人も、メガネをかければ遠くも近くもはっきり見えます。 ところが、40歳を過ぎると、なんとなく眼が疲れたり、長時間パソコンを見つめていると肩がこったりしませんか。 もっと年齢を重ねると、新聞の活字が読めなかったり、書類の細かい数字を間違えたりした経験はありませんか。
40歳を過ぎると、誰でも老眼(老視)が始まります。遠くが良く見えていた人は、正視や遠視の可能性があります。 もともと遠くがはっきり見えていた人ほど、老眼の症状が強く出ます。 近視の人でも、コンタクトレンズを使用している時は、正視や遠視の人と同じように、老眼で近くが見えにくくなります。
老眼は、ピントを合わせる水晶体が固くなって、近くがはっきり見えなくなる状態です。 水晶体以外にも、瞳孔(どうこう・・ひとみのこと)の大きさによる影響もあります。 薄暗いところでは、瞳孔が大きくなるため、焦点深度が浅くなって見えづらくなります。 本や新聞を読むときは、明るい照明を選ぶ必要があります。
老眼は治りませんが、メガネなどの道具を活用することで、快適な生活を過ごすことができます。 近視の方は、メガネをはずすと近くが見えます。 強い近視の方は、パソコン画面や仕事に合わせて、度の少し弱いメガネをかけると良いでしょう。 遠視の方は、近くにピントを合わせるのが大変なので、近くを見るために専用の厚いメガネ(老眼鏡)が必要です。 老眼鏡は、遠くは見えません。運転するためには、別のメガネが必要です。 遠近両用のメガネ、遠方と中間距離の両方に合わせたメガネ、中間と近方に合わせたメガネなど、仕事や環境によって、 一人一人が必要とするメガネはさまざまです。
メガネは基本的に一定の距離にしかピントが合いません。 自分が最も必要とする距離にメガネを合わせないと、せっかくメガネを作っても満足しないでしょう。 まず、自分の必要とする距離が、何センチメートルかを正確に知ることが必要です。 その上で、眼科専門医に自分の希望を伝えて、眼鏡処方せんの交付を受けるとよいでしょう。 どうぞ、ご自分のメガネを持って、眼科専門医にご相談ください。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
コンタクトレンズあれこれ (第7回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
日本の人口は約1億2000万人ですが、そのうちの4000万人は近視です。多くの人は眼鏡を使っていますが、コンタクトレンズの使用者も、1500万人以上です。初期のコンタクトレンズは、すべてハードコンタクトレンズでしたが、今では、ソフトコンタクトレンズを使用している人が大部分です。
こんなに、コンタクトレンズ使用者が増えたのは、使い捨てソフトコンタクトレンズの誕生に大きな理由があります。
世界で始めてコンタクトレンズの実験をした人は、レオナルド・ダ・ビンチといわれています。レオナルド・ダ・ビンチは、16世紀初頭、金魚鉢のようなガラスボールに水を満たして顔を入れると、ガラス越しによく見えることを証明しました。17世紀にフランスのデカルトも、水で満たしたガラスの筒で実験したことがわかっています。
私たちが思い浮かべるようなコンタクトレンズは、20世紀前半に登場しました。はじめは、ガラス製、次にプラスチック製のレンズが登場しました。今のものより硬くて大きなハードコンタクトレンズでした。やがて、小さくてやわらかい、硯在のハードコンタクトレンズが開発されました。ソフトコンタクトレンズは30年前に登場しました。
現在では従来型のものから、コールド消毒ができる2週間タイプや、毎日交換する使い捨てソフトコンタクトレンズが主流になってきました。使い捨てソフトコンタクトレンズは、装用感もよく、使用者人口がどんどん増えています。
では、使い捨てソフトコンタクトレンズは安全なのでしょうか。日本眼科医会の調査では、コンタクトレンズ使用者の1割に、眼障害を認めています。その3分の2はソフトコンタクトレンズによる眼障害でした。特に、充血、角膜の上皮びらんや浸潤、点状混濁などがみられました。眼障害は、使用時間が1日8時間以内の人に少なく、1日16時間以上の人に、とっても多い結果でした。とりわけ、視力障害を残すような重症な角膜障害は、ソフトコンタクトレンズが、ハードコンタクトレンズの2倍も起こしやすいことがわかりました。
コンタクトレンズは、角膜にじかに触れるものです。植込型ペースメーカーや人工心臓弁などと同じように、医師の処方が必要な「高度管理医療機器」です。必ず、定期的に眼科専門医の診察を受けて、安全にコンタクトレンズを使用することが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
加齢黄斑変性ってなに? (第8回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
『加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)』という病気を聞いたことがありますか。初めて耳にする人が多いことと思います。熱心な方は、最近のテレビの健康番組や雑誌で目にしたことがあるかもしれません。加齢黄斑変性という病気は文字通り、年齢が進むことによって(=加齢)、網膜の真ん中の一番視力の出るところ(=黄斑)が、変化して働かなくなり(=変性)、ついには見えなくなってしまう病気のことです。
なんだか、とっても恐ろしい病気に聞こえます。なぜ、最近の話題になっているかというと、加齢黄斑変性が増えてきているからです。失明原因といえば、白内障、緑内障、糖尿病網膜症などがありました。今では、白内障は手術をすれば、元の視力を回復することができます。白内障で失明する人は、特別な場合に限られてきました。緑内障と糖尿病網膜症は、日本では失明原因の1位と2位を占めています。では、米国の失明原因の1位は何でしょう。『加齢黄斑変性』なのです。現在の日本でも、失明原因の第3位になっています。日本でも、将来は米国と同じように、失明原困の第1位になる可能性があります。
加齢黄斑変性の初期症状は、ものがゆがんで見えることです。細かいものが見えなくなったり、直線が波打って見えたりします。ほとんどの人は、片目だけの症状なので、普段は気づきません。たまたま、良い方の目を隠して、片目で見たときに気づきます。ゆがみが大きくなったり、見えにくい範囲が大きくなったりして気づく事もあります。
網膜が変化して見えなくなる病気ですが、黄斑変性の中にも種類があって、治療によって進行を食い止め、視力の回復を期待できるタイプもあります。加齢黄斑変性は、ゆっくり進行する慢性疾患ですが、精密な検査(眼底検査、視野検査、造影剤で撮影する検査など)で黄斑変性のタイプを調べて、内服治療、レーザー治療、注射した薬物とレーザーを併用する光線力学療法、手術治療(硝子体手術)などの治療方法の中から、効果の期待できる治療を選択することになります。
この病気の原因は、遺伝的素因と環境因子の両方が考えられています。喫煙が加齢黄斑変性の悪化を招くことは間違いないようです。禁煙と生活習慣病の予防が加齢黄斑変性の予防になります。今からでも遅くはありません。生活習慣を改善し、もし、気になることがあれば、眼科専門医にご相談ください。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
冬につらいドライアイ (第9回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
ドライアイという言菓を聞いたことがない人はいないでしょう。日本には約800万人のドライアイの息者さんがいると推定されています。一説では、自覚症状のない人を含めると2000万人近くがドライアイと言われています。
ドライアイの症状は目が疲れやすい、目がしょぼしょぼする、目がごろごろする、目が重たい、目やにが出る、目が赤くなる、目が乾くなどが含まれますが、実は目が乾くと訴える人は、そう多くありません。ドライアイは涙の量が少なかったり、涙の性質が変化して、うまく働かなくなったりして症状が出ます。涙には、涙腺から出てくる水分だけでなく、油分やネバネバした成分(ムチン)も含まれ、バランスよく目の表面を保護しています。水、油、ネバネバの3種類が揃っていないと、ドライアイの症状が出てしまいます。
涙の水分が足りなくなっても、油やネバネバがあると、いつも目の中に涙がたまっているような気がします。本当はドライアイなのに、反対に涙が多いと間違っている人がいます。目じりに、常に涙がたまり、いつもふき取っている方に、あなたはドライアイですよ、といっても信じてもらえません。細長い紙で涙の量を測る検査(シルマーテスト)で、水分が少ないのが証明されて、はじめてドライアイに気づくわけです。
冬は、空気中の水分が減って乾燥するため、ドライアイにはつらい季節となります。北海道では、暖房が入るため、ますます乾燥が進みます。夜間の睡眠中は、まばたきをしないため涙液が減少します。朝、目が覚めた時に、ドライアイの症状が強くなるのは、このためです。
ドライアイの一番の対策は、まばたきを増やすことです。テレビを見たり、パソコンに向かったりすると、まばたきが減ってしまいます。テレビやパソコンのディスプレーは、低い位置において、視線を下向きに保つと良いでしょう。部屋の加湿を心がけ、直接目に風が当たらないように気をつけます。
眼科では、ドライアイの治療に、人工涙液や角膜保護薬の点眼を行います。必要に応じて、抗菌薬や抗炎症薬の点眼も併用します。もっと重症な方には、涙点プラグで、涙の出口をふさぐ方法もあります。ドライアイの中には、シェーグレン症候群のように全身の病気もあります。目に自覚症状が出たときは、すぐに眼科専門医の診察を受けて、適切な治療を受けると良いでしょう。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
北海道のアレルギー性結膜炎 (第10回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
アレルギー性結膜炎とは、アレルギーを起こす物質(アレルゲンといいます)が、目の中に入って、結膜に炎症などのアレルギー反応を起こした状態をいいます。鼻に炎症を起こせばアレルギー性鼻炎、気管支に炎症を起こせば気管支ぜんそくになります。わが国では、人口の約30%が、何らかのアレルギー性疾患を持っているといわれています。
目の表面は、まぶたやまつげによって、外から花粉やほこりが入らないようにバリアの役目をはたしています。もし、目の表面についてしまっても、涙で洗い流すようになっています。ところが、アレルギーのある人では、目がかゆくなり、痛みが加わり、目をこすらずにはいられなくなります。悪化すると、まぶたがはれたり、充血して白目の結膜がはれたり、目やにが出たりします。
アレルギー性結膜炎には、季節性のものと通年性のものがあります。季節性のアレルギー性結膜炎の代表例は、花粉症です。原因物質のアレルゲンの種類によって、すぎ花粉症、シラカバ花粉症などといいます。北海道では、シラカバ花粉症が4月から6月にかけて多くみられます。シラカバアレルギーの人は、りんご、もも、さくらんぼなどを食べると、口やのどがひりひりしたり、はれたりすることがあります。シラカバと同じバラ科の植物に共通な部分があり、口の中でアレルギー反応を起こすためです。通年性のアレルギー性結膜炎では、家のなかにあるほこり(ハウスダスト)がアレルギーの原因になります。ハウスダストには、ダニや髪の毛、フケ、カビなど合まれ、一年中、病気の起こる可能性があります。
アレルギー性結膜炎の予防は、病気を起こすアレルゲンから離れることです。花粉症の場合は、外出を避け、ゴーグルやマスクの着用が有効です。洗眼は、目にキズをつける可能性があり、すすめられません。ハウスダストの予防は、こまめな掃除と部屋の換気です。特に寝具の手入れが重要です。
治療には、抗アレルギー薬の点眼が効果的です。抗アレルギー薬にも複数あって、季節性アレルギー性結膜炎では、花粉の飛ぶ前から点眼を開始すると、症状を予防したり、症状を軽くしたりできるタイプもあります。重症の場合は、ステロイドを含んだ点眼薬を使用することもあります。いずれの場合も、眼科専門医とよく相談して、ひとりひとりに合った治療法を選択することが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
早期発見で治る網膜剥離 (第11回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
「網膜剥離」という病気を聞いたことがあると思います。ある日、急に飛蚊症が強くなって、視界の端のほうから、だんだん見えなくなり、時間とともに、すっかり見えなくなってしまうのが典型例です。網膜剥離は、1万人に1人の割合で起こる病気です。道内では1年間で、約500人が網膜剥離になっています。
眼球はカメラのような構造をしています。目の中に入った光は、カメラのフイルムやCCDに相当する網膜で光を感じています。この網膜がはがれてしまうのが網膜剥離です。網膜がはがれると、網膜内の物を見る細胞(視細胞)に栄養が行かなくなり、視細胞が死んでしまいます。網膜剥離が治っても、視細胞が働かなければ、物は見えません。
網膜剥離は、網膜に穴が開いたり、網膜が裂けたりし、網膜の下に水が入り込んで、網膜がはがれてしまうのが原因です。これを裂孔原性(れっこうげんせい)網膜剥離といいます。はじめに、黒い点や、虫、ゴミみたいなものがみえたり(飛蚊症)、目のなかで光が見えたりすることもあります。いきなり、片方の眼の周辺部が見えなくなったり、近くも遠くも見えなくなったりすることもあります。
治療は、網膜の穴や裂孔を全てふさいで、網膜の下の水を取り除いて、網膜の位置を元に戻します。網膜の位置が戻れば、網膜剥離は治ったことになります。この手術(網膜復位術)は、入院治療が必要です。もし、網膜剥離が狭い範囲に限局していれば、穴や裂孔をふさがないで、はがれた網膜の周囲にレーザー光凝固を加えて、網膜に癒着をつくり、剥離の進行を止める方法を行います。レーザー治療だけであれば、外来通院で治療可能です。
早期に見つかれば、95%の網膜剥離は治すことができます。しかし、視力の回復は、網膜剥離の期間や程度に左右されます。視細胞が障害される前に、急いで治療する必要があります。
網膜剥離には、裂孔原性網膜剥離だけでなく、物がゆがんで見える漿液性(しょうえきせい)網膜剥離や、糖尿病網膜症でみられる牽引性網膜剥離があります。網膜剥離の種類によって、治療方法も異なります。網膜剥離は、片方の目だけに起きることがほとんどです。両目で見ていると、なかなか気づきません。普段から、片目だけで見るくせをつけて、気になる変化があれば、すぐに眼科専門医の診察を受けることが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
日帰り手術と白内障手術 (最終回) 〜視界良好〜 |
|
|
|
眼科の手術には、日帰りで行われる手術と入院して行われる手術があります。糖尿病網膜症の治療に行われるレーザー網膜光凝固術や、麦粒腫の切開術は、入院しないで治療が行われます。網膜剥離手術や硝子体手術、多くの緑内障手術は入院して治療が行われます。昔の白内障手術は、全て入院して行われました。今の白内障手術は多くの施設で、日帰り手術として実施されています。
日帰り手術と入院手術には、それぞれ長所と短所があります。日帰り手術の長所は、費用が安いこと、住み慣れた自宅で休息できること、ある程度の仕事を続けながら治療できることなどです。これは、入院手術では、そのまま短所になります。入院手術では、費用が高いこと、不慣れな病室にいること、仕事ができないことなどです。反村に、入院手術の長所は、通院の必要がないこと、術後の安静が十分に取れること、術後に変化があってもすぐに対応できることです。これらは日帰り手術の短所にもなります。
では、白内障手術はどうでしょうか。日帰り手術の方が、費用が安い、自宅で休息できる、仕事に早く復帰できることが長所です。自内障手術を受けても安静は必要ないのでしょうか。白内障手術も、からだの一部にメスを入れるのですから、炎症が起きてしまいます。手術直後は、目の安静が炎症の早期沈静に有効です。
白内障手術は、小さな切開で手術を行い、手術後の合併症も少ない手術です。手術当日でも、眼帯をして地下鉄やバスで通院が可能です。
ただし、どんなに短時間で終わる手術でも、絶対安全な手術というものは存在しません。白内障手術は短時間で終了しますが、簡単な手術ではありません。日帰り手術であっても、付き添いは必要です。手術後は医師の指示を、しっかり守らなくてはいけません。
網膜剥離手術はどうでしょうか。網膜剥離は、剥がれた網膜が元の位置に戻らないと治りません。手術後に安静が必要なので、入院手術が安全です。多くの緑内障手術や硝子体手術は、術後の合併症の予防や早期回復のため、入院して治療を受けた方がよいでしょう。いずれも疾患の程度や手術方法の選択によつて、日帰り手術が可能な場合もあります。一人ひとりの症状や程度によって、治療法の選択枝が変わります。眼科専門医とよく相談して、自分で納得できる治療法を選ぶことが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
飛蚊症 (第1回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−正体は「溶けた硝子体」− |
|
|
|
目は物を見るためにできた体の一部です。景色を見たり、本や新聞を読むためにありますが、時に見る必要のないものまで見えることがあります。
五十歳近くの女性が受診しました。「明るい青空を見ていると、急にたくさんの虫が飛んできた。目の前で動いているので、手を振ってどけようとしても、さっぱり虫がいなくならない」と訴えました。
人の目は外の光が眼球の中に入って、網膜が光を感じることで、見えるようになっています。眼球の一番外側の角膜から網膜まで、光がよく通るように透明につくられています。途中にはピントを合わせる水晶体と、ゼリーのような硝子体(しょうしたい)があります。
硝子体は子どものころは少し固めですが、年をとるにつれて柔らかくなり、一部は溶けて混濁します。溶けた部分は水のようになり、目の中で流れるように動くことになります。
これが、虫の飛ぶように見える飛蚊症(ひぶんしょう)の原因です。飛んで見える形はさまざまで、虫だったりゴマ粒だったり糸状だったり、輪ゴムのように見えることもあります。背景が白いときに、はっきり見えます。
飛蚊症には加齢によって現れる生理的飛蚊症と、病的な飛蚊症とがあります。生理的な飛蚊症は、近視の人ほど早くから出現し、十代から見えることも。四十歳を過ぎると、硝子体が網膜からはがれることがあります。後部硝子体剥離(はくり)という加齢現象です。このとき、ちぎれた細胞が飛び出して、飛蚊症を起こすのです。受診された女性は、まさにこの症状でした。
病的な飛蚊症は、糖尿病網膜症などによる硝子体出血、網膜剥離、ぶどう膜炎など目の炎症によるものなどです。時に眼内腫瘍(しゅよう)が見つかることもあります。
生理的な飛蚊症は治療の対象になりませんが、病的なものは放置すると失明することもあります。単なる加齢現象と考えずに、眼科専門医の診察を受けることが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
白内障 (第2回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−ほとんどは加齢が原因− |
|
|
|
白内障はお年寄りの病気と考えていませんか? 白内障は赤ちゃんから老人まで、全年齢の人に発症する病気です。
生まれたばかりの赤ちゃんに起きる白内障を先天白内障といいます。生まれてすぐに、目の瞳孔が白いことに気づきます。小学生や中学生ぐらいでも、先天白内障が進行したり、糖尿病や外傷、炎症によって白内障が起きることもあります。三十歳、四十歳で発症することもあります。
五十歳くらいの男性が「右目のメガネが合わない」と受診されました。ここ数年、近視が進行し、毎年のようにメガネを交換していたそうです。検査してみると、両目に白内障が見つかり、特に右目に強いことが分かりました。
目の中にある水晶体は、透明な凸レンズの形をしています。ものを見るときにピントを合わせる働きがあります。この水晶体が濁ってくることを、白内障といいます。白内障になると、ものがかすんで見えたり、まぶしくなったり、ぼやけて二重三重に見えることもあります。水晶体の中心部分(核)が強く濁ると、かすむだけでなく、近視も進行します。この男性の近視が進行するのは核白内障のためでした。
ほとんどの白内障は加齢が原因です。高齢の方ほど白内障の発症が多く、七十歳になると、90%以上の人に白内障が見られます。
初期の白内障は、点眼薬が進行を遅くするので有効です。白内障の混濁をとる方法は、今のところ手術治療以外にはありません。現在の白内障手術は、短時間で終わり、日帰り手術も可能です。濁った水晶体を小さな切開創から取り除き、かわりに折りたたみ式の眼内レンズを挿入します。
傷口が小さいので、早く仕事に復帰することができます。ただ、残念ながら眼内レンズは単焦点です。遠くや近くの両方に都合よくピントを合わせることができません。手術で視力が戻ってもメガネは必要です。
手術時期は白内障の程度や不自由さによって、さまざまです。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
緑内障 (第3回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−眼圧下げ進行遅らせる− |
|
|
|
緑内障という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。白内障は手術をすれば治りますが、緑内障は根本的な治療法がないので、怖い病気だと考えている人も多いでしょう。緑内障になると、どんな症状が出るのでしょうか。
四十歳の女性が緑内障が心配だと受診しました。「先日、片方の目を隠して見たら、視野の一部に暗く見えないところがある」と訴えました。
緑内障にはたくさんの種類があります。大きく分けると、原因不明の「原発緑内障」、他の病気で起きる「続発緑内障」、生まれつき異常が見られる「先天緑内障」に分けることができます。
最も多くみられるのが原発緑内障で、強い痛みとともに短時間で失明する急性のタイプと、長い時間をかけて少しずつ視野が欠け、最後に失明する慢性のタイプに分類できます。
急性の緑内障は眼球の隅角(ぐうかく)という部分が閉じて、水が流れなくなってしまう原発隅角閉塞(へいそく)緑内障が代表例です。夜間など瞳孔が開いたときに起きやすく、目の痛みや頭痛のため、内科や脳神経外科を受診する人もいます。
慢性的な緑内障は目の痛みや充血はみられず、たまたま眼圧検査や眼底検査を行って見つかることが大部分です。代表的な原発開放隅角緑内障は、眼圧が低い正常眼圧緑内障を含めると、日本に二百万人以上いるといわれています。隅角の異常で水の流れが悪くなり、視神経が犯されて徐々に視野が欠けていきます。受診された女性のように、たまたま片方の目で見て、偶然自覚できることもあります。
緑内障は眼圧を下げることで進行を遅らせたり、止めたりすることができます。治療の中心は点眼薬です。現在は多くの種類の点眼薬が開発され、効果的に眼圧を下げることができます。ただ、薬による治療で効果がみられない場合は、眼球の一部を切開し、たまった水を流す経路を設けるための手術治療が行われます。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
はやり目 (第4回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−タオル別々 手洗いまめに− |
|
|
|
保育園や幼稚園で、たくさんの子供たちが次々に結膜炎になることがあります。家族の一人が結膜炎になり、治ったころに別の家族がなってしまうことを「はやり目」といいます。
はやり目は結膜炎の中でも感染力が強い流行性角結膜炎、咽頭(いんとう)結膜熱、急性出血性結膜炎の三つを指します。いずれもウイルスが原因です。結膜は目の表面の白目のところにある透明な組織です。炎症を起こすと、目やに、充血、涙目、ごろごろ感、まぶしさ、、、などが出現します。
四歳の子供が、目やにと充血で受診しました。二週間ほど前、兄弟に同じ症状があったそうです。のどの痛みや発熱はありませんでした。
流行性角結膜炎は、アデノウイルスの八型、一九型、三七型が原因で、潜伏期が一〜二週間あります。症状は突然、たくさんの目やにが出て、ごろごろして、数日で両目に結膜炎が起きます。
ウイルスは、目やにの中にたくさんいますから、目をこすった後に触ったところや、顔を洗ったときのタオルから感染します。結膜炎は約二週間続き、角膜に炎症を起こして視力障害の原因になることもあります。受診された子供は、この病気でした。
アデノウイルス三型、四型、七型に感染すると、結膜炎だけでなく、のどの痛みや三九度近い熱が出ます。咽頭炎を合併することから咽頭結膜熱と呼びます。潜伏期は一週間程度で、発症してから二週間くらいで治ります。治ってからもウイルスを出し続け、プールで感染しやすいので、プール熱とも呼ばれます。
急性出血性結膜炎はエンテロウイルス七〇型が原因です。一〜二日の潜伏後、結膜が真っ赤に出血し、目やにが出て結膜炎になります。アポロ11号が月に着陸した一九六九年に大流行したので、アポロ病ともいいます。
はやり目の治療に特効薬はありませんが、抗菌薬や抗炎症薬を点眼します。はやり目と診断されたら、よく手を洗い、タオルは別々にして、他の人にうつさないことが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
加齢黄斑変性 (第5回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−網膜の中心部に異常− |
|
|
|
私たちは目の奥にある網膜でものを見ています。特に網膜の中心にある黄斑(おうはん)という所に、たくさんの視細胞が集まっていて、細かいものを判別しています。良好な視力を得るためには、黄斑が正常に働く必要があります。
五十五歳の男性が「偶然、右目で見たときに何だかおかしかった。ゆがんで見えるようだ」と訴えて受診しました。
目は二つあるので、片方の目に異常が起きてもなかなか気づきません。両目に病気が起きたり、偶然片方を閉じたときに異変に気づきます。この男性は加齢黄斑変性という病気でした。初めて聞く人も多いと思いますが、この病気は年をとることによって(加齢)、ものを見る大事な所(黄斑)が、変化して働きが悪くなり(変性)、見えなくなってしまうものです。
加齢黄斑変性には、二つの種類があります。一つは年齢とともにゆっくりと網膜の働きが障害されて、視力が低下するタイプで委縮型といいます。もう一つは網膜の下にある脈絡膜から血管が伸びて、網膜が腫れたり、出血して黄斑を壊してしまうタイプで滲出(しんしゅつ)型といいます。
多いのは滲出型で、初めのうち線を見たときにゆがみが出たり、暗く見えづらい部分が出て、進行すると急激に視力が低下します。五十歳以上に多く、女性よりも男性に多いことが分かっています。三分の一の人は両目に起きています。
滲出型は、レーザー治療により進行を遅らせたり、改善できることがあります。委縮型は残念ながら治療法はありません。
この病気の原因は遺伝的素因と環境因子の両方が考えられています。現在、米国の中途失明の第一位は加齢黄斑変性です。
もともと日本人に少ない病気でしたが、生活環境(食生活)の欧米化とともに、日本人にも増えてきています。特に喫煙の影響が大きいとされ、禁煙と生活習慣病を防ぐことが、加齢黄斑変性の予防になるでしょう。
|
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
コンタクトレンズの合併症 (第6回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−ケア怠ると重い障害も− |
|
|
|
日本でコンタクトレンズを使用している人は千五百万人以上といわれています。コンタクトレンズにはハード、ソフト、二週間使用の使い捨て(頻回交換レンズ)、一日のみ使用の使い捨て、度の入っていないカラーレンズ、医療用のレンズがあります。
二十五歳の女性が「コンタクトレンズを入れると目が痛い」と訴えて、受診しました。コンタクトレンズは二週間使用できる頻回交換レンズでした。両目とも充血し、痛みで涙を流していました。
コンタクトレンズは目の中に入れるものですから、心臓ペースメーカーと同じように、法律で危険性の高い高度管理医療機器に含まれます。使用方法を守らなかったり、取り扱いを間違えると角膜や結膜など、目に重大な障害を引き起こします。
コンタクトレンズを使用すると、視界が広くなり、スポーツをするときにも大変便利です。女性には美容上の観点からも好評です。特にソフトコンタクトレンズは装用した感覚もよく、思わず長時間使用してしまうこともあります。
ただ、コンタクトレンズは目の中に入れている間に汚れます。ソフトはハードに比べ、汚れや細菌がつきやすいため、毎日のレンズケアが必要です。
毎日使い捨てるタイプは、汚れても使うたびに捨てるので、毎回きれいな新品です。普通のソフトコンタクトレンズや二週間タイプのものは、外した後に必ず消毒や洗浄を行わないと、思わぬ合併症を起こしてしまいます。
受診した女性はケアをあまりしていませんでした。汚れたコンタクトレンズや長時間の装用は、充血や異物感、涙が出続ける症状などを生じて、角膜混濁や角膜浸潤(黒目の中に白血球が集まる状態)を起こし、視力障害の原因になることもあります。
コンタクトレンズと保存容器は常に清潔に保つように心がけましょう。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
ぶどう膜炎 (第7回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−視力障害続き重症化も− |
|
|
|
「目に炎症が起きている」と言われると、結膜炎や角膜炎を思い浮かべる人が多いでしょう。でも、ぶどう膜炎という聞き慣れない炎症もあります。
四十歳の女性が「目がかすんで、近くも遠くもよく見えない」と訴えて受診しました。詳しく検査してみると、ぶどう膜炎であることが分かりました。
ぶどう膜は目の中の虹彩、毛様体、脈絡膜の三つからできています。三つとも、色素がたくさんあり、まるでブドウのような色をしていることからその名前が付きました。
虹彩が炎症を起こすと虹彩炎、毛様体も同時に炎症を起こすと虹彩毛様体炎、脈絡膜が炎症を起こすと脈絡膜炎となり、これらを合わせてぶどう膜炎と呼びます。
ぶどう膜炎になると、目の痛みや充血が出てきます。角膜炎や結膜炎のような強い充血は見られず、目やにも出ません。視力が下がったり、霧がかかったように見えることもあります。炎症によって目の中が濁ったり、目の奥が腫れて、かすみの原因になります。
ぶどう膜炎自体は珍しい病気ですが、ひとたび炎症を起こすと繰り返したり、視力障害が続いて重症化しやすくなります。中でもサルコイドーシス、ベーチェット病、原田病という病気が多く見られます。これらの病気は目だけでなく、全身にも症状が出ます。
特にサルコイドーシスとベーチェット病は、いずれも厚生労働省指定の難病です。目の症状だけでなく、リンパ節がはれたり、微熱が続いたり、口の中に潰瘍(かいよう)ができたり、頭痛や耳鳴りなど全身に症状が出ます。
ぶどう膜炎の治療は点眼薬が中心ですが、重症の場合は目の周りに注射をしたり、内服薬で強力に炎症を抑えることもあります。
全身症状が表れたり、視力障害が強いときは、入院して治療することもあります。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
アレルギー性結膜炎 (第8回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−こまめな掃除が予防に− |
|
|
|
アレルギー性結膜炎と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは花粉症でしょう。毎年、春になると花粉のためにくしゃみや鼻水が出て、アレルギーのある人はつらい思いをします。
花粉症は特定の時期に見られるアレルギー症状で、本州のスギ花粉によるアレルギー性結膜炎が有名です。ところが、一年中みられるアレルギー性結膜炎も存在するのです。
人の体は外から入ってきたものを排除したり、害が及ばないようにする働きがあります。これが過剰に働いたりして、自分自身に害を及ぼすのが、アレルギーです。
アレルギー性結膜炎では、アレルギーを起こす物質が目の中に入り目がかゆくなったり充血し、目をこすると痛みます。まぶたや白目が腫れたり、目やにが出ることもあります。
北海道では四月から六月にシラカバによる花粉症が多く見られます。このような季節性のものに対して、一年中、症状が続くものを通年性アレルギー性結膜炎といいます。原因は家の中のほこりに混じっているダニや髪の毛、フケ、カビなどさまざま。これらをまとめて、ハウスダストと呼んでいます。
断熱性に優れた北海道の家は、冬も温かく、ダニの繁殖に好都合です。特にじゅうたんはダニの絶好のすみかといわれています。
アレルギー性結膜炎の予防は病気を起こす物質を避けることが一番です。ハウスダストを減らすため家の中をこまめに掃除し、換気をよくして、ダニやカビを増やさないことが大切です。治療は抗アレルギー薬の点眼が有効で、季節性の結膜炎には花粉の飛び始める前から使用すると効果的です。症状が強い場合はステロイドを含んだ点眼薬を使用することもあります。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
糖尿病網膜症 (第9回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−症状なくても眼底検査を− |
|
|
|
国内の糖尿病患者は約七百万人と言われています。糖尿病予備軍を含めると日本人の十人に一人は糖尿病か、糖尿病になりかけているということになります。
五十歳の男性が糖尿病の検査のために受診しました。「数年前に眼科を受診したとき、『眼底出血が少しある』と医師に言われた」そうです。
糖尿病は自覚症状の表れにくい病気です。健康診断や風邪をひいたときの検査で発見された人も多いと思います。糖尿病を放置すると、目が見えなくなることはよく知られていますが、糖尿病網膜症も自覚症状が出にくい病気です。
糖尿病網膜症の多くは五年以上糖尿病が続く人に起きています。ところが、ほとんどの人は、いつ糖尿病になったのか分かりません。血糖値が高いことで、細い網膜の血管が障害を受けて次第に目詰まりし、出血したり、血管にこぶができ、網膜が腫れます。初めのうちは出血や分泌物がたまる白斑が表れて単純糖尿病網膜症と呼びます。自覚症状は全くありません。
網膜症が進行すると、目詰まりした血管が増えて、網膜の腫れが広がり、網膜の中に正常ではない新しい血管(新生血管)ができてきます。この段階(前増殖糖尿病網膜症)になると、レーザーで治療する網膜光凝固治療が必要です。
さらに進行すると新生血管がたくさんでき、目の中の全体に出血したり、網膜剥離(はくり)や緑内障になったりして、急激に視力が低下します。このような増殖糖尿病網膜症になると、網膜光凝固治療だけでなく、目の中を手術する硝子体手術も必要になってきます。
受診した男性は前増殖糖尿病網膜症でした。造影剤を注射して眼底写真をとって見ると、レーザー治療が必要なことが分かりました。糖尿病で視力が下がったときは網膜症が進んだ状態です。糖尿病と診断されたら自覚症状がなくても、定期的に眼底の検査を受けることが重要です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
ドライアイ (第10回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−まばたき増やし予防を− |
|
|
|
ドライアイは文字通り目が乾燥しドライになった状態を指します。では、目が乾くとは、どんな症状なのでしょう。
涙は水分と油、ネバネバ成分の三種類からできています。この三つがバランスよく働くことで、目にうるおいを与えます。まばたきをすることで涙が目の表面を覆い、目を保護します。
涙腺から出る水分の量が少ないと、涙が不足してドライアイになります。水分が足りなくても、油成分やネバネバの成分が残って、涙がたまっているように感じることもあります。水分の量が十分でも油成分が少ないとすぐに蒸発して、ドライアイになります。
ドライアイは涙の量が減っても、涙の質が悪化しても起きるのです。目がしょぼしょぼする、目が疲れやすい、目やにが出る、乾いた感じがする、目がごろごろする…。症状はさまざまで、時には涙が出る、と訴える人もいます。
年をとると誰でも涙の量は減ってきます。全身の病気や薬の副作用で、ドライアイになることもあります。パソコンに熱中すると、まばたきが減ってしまいます。部屋の乾燥やコンタクトレンズが原因のこともあります。
ドライアイの対策はまばたきを増やすことです。パソコンやテレビの画面は低い位置に置き、視線が下向きになるようにしましょう。北海道は冬が乾燥しがちなので、部屋の適度な加湿も必要です。温風などに直接当たらない工夫も大切です。
治療は人口涙液や角膜保護薬の点眼が中心です。必要に応じて抗菌薬や抗炎症薬を併用します。重症例では涙の出口をふさぐ治療もあります。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
複視 (第11回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−大病が原因のケースも− |
|
|
|
人の目は二つありますが、物が二重に見えることはありません。右目と左目は少し離れていますが、いつも一つに見えるようになっています。
七十歳の男性が「運転中にセンターラインが二本見えることに気づいた」と訴え、受診しました。
物が二重に見えることを複視といいます。両目が別々の物を見ていると、頭に二つの情報が入ってしまい、二重に見えることになります。二重に見えても片方の目を隠すと、一つしか見えなくなります。
複視は目を動かす神経や筋肉の障害で、左右どちらかの目の動きが悪くなったり、目の位置がずれることで起きます。正面では異常がなくても、横を見たり、上や下を見たときに複視が強くなることもあります。複視は原因不明のこともありますが、糖尿病や脳動脈瘤(りゅう)、脳卒中、脳腫瘍(しゅよう)など大きな病気が原因のときも少なくありません。
幼いころから斜視の人は、左右の目が別々の物を見ていても、頭の中で片方の映像を無意識に消しているため、複視は自覚しません。その代わり、立体的に物を見ることはできません。
受診した男性は糖尿病に合併した神経障害で、眼球運動が制限され、複視になったことが分かりました。
一過性で回復することもありますが、複視が続く場合は手術が必要になることもあります。急に物が二重に見えたときは、大きな異常が隠れているかもしれないので、眼科での詳しい検査が必要です。
複視によっては片方の目で見ても症状が続く場合もあります。これを単眼複視といいます。最も多いのは乱視です。乱視の時は物が二重に見えることがあります。白内障が進んだ時にも複視を自覚することがあり、月を見たときに二重三重に見えることもあります。単眼複視は眼球の異常なので、眼鏡をかけたり、手術でよくなります。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
眼底出血 (第12回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−物が見えなくなることも− |
|
|
|
健康診断で目の写真を撮ったり、眼科を受診したときに「眼底出血がありますよ」と言われるとビックリしてしまいます。そう言われても自覚症状のないことがほとんどです。
眼底には物を見るための網膜があります。この網膜とその周囲に表れた出血を眼底出血といいます。鏡を見ても気がつきません。白目の出血を眼底出血と間違える人もいます。これは目の表面だけの出血で、結膜下出血と言い眼底出血とは異なります。
五十歳の男性が人間ドックの目の検査で、眼底出血を指摘され、受診しました。調べてみると網膜静脈分枝閉塞(へいそく)症という病気でした。網膜以外では静脈が詰まっても、血液が自然に他の静脈へ流れる道ができて出血しません。しかし、網膜は非常に薄いので、静脈が閉塞してしまうとほかに流れる余裕がなく、出血してしまいます。
なぜ、静脈が閉塞するのでしょう? 網膜では動脈と静脈が所々で交差しており、動脈硬化などで固くなった動脈が、静脈を押しつぶすからです。視神経の所で閉塞すると網膜中心静脈閉塞症になり、枝分かれした所だと網膜静脈分枝閉塞症です。
網膜中心静脈が閉塞すると突然、見えなくなってしまいます。網膜静脈分枝閉塞症だと、閉塞した場所によって障害の程度が異なります。視力に大事な黄斑部が含まれると、やはり見えなくなります。受診した男性は黄斑部が無事だったので、自覚症状がありませんでした。
放置すると、新たな血管ができて大きな出血を起こしたり、網膜はく離などの合併症を起こすこともあります。閉塞部位に応じて薬物治療やレーザー治療、手術が必要になります。
眼底出血は糖尿病網膜症や外傷、炎症でも起きます。網膜に穴が開き、眼底出血だけでなく、硝子体出血が起きることもあるので、出血の原因に応じた治療が必要です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
赤ちゃんの目の病気 (第13回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−涙や目やに 親が注意を− |
|
|
|
赤ちゃんにも目の病気があります。赤ちゃんは病気があっても訴えないので、親が普段からよく注意していないと気づかないこともあります。
生後三カ月の赤ちゃんが「片方の目から涙が出る」と受診しました。いつも目がうるうるし、横を向くと外に流れるそうです。
涙は上まぶたの耳側の奥にある涙腺から出てきます。目にたまった涙は、まぶたの鼻側にある涙点という穴から鼻涙管(びるいかん)を通って鼻の中に流れます。
生まれたばかりの赤ちゃんも流れるようになっていますが、赤ちゃんによっては鼻涙管が閉じたままで生まれます。受診した赤ちゃんは、この先天性鼻涙管閉塞(へいそく)でした。
涙が流れないため途中の涙嚢(るいのう)というところに細菌が入って涙嚢炎を起こすこともあります。眼科医の指導で涙嚢部を圧迫するマッサージを繰り返すと、ほとんどの赤ちゃんは涙が流れるようになります。効果がない場合は細い針金を通して、閉塞部を治します。
赤ちゃんに涙が出るときは、逆さまつげが原因のこともあります。赤ちゃんの顔は鼻が低く、ふっくらしているので、下まぶたのまつげが内側に向きがちで、睫毛(しょうもう:まつげ)内反といいます。
まつげが柔らかいので角膜に触れても、たいてい大丈夫なのですが、角膜にキズがつくと涙が出ます。充血したり、目やにが出るときは点眼治療を行います。大きくなっても治らなければ、手術を行うこともあります。
目が寄っていたり、離れたりしているのを斜視といいます。生まれてすぐに斜視があれば目の中に病気があるかもしれません。網膜の異常や眼内の腫瘍(しゅよう)が見つかることもあります。
白内障や緑内障のこともあります。瞳孔が白かったり、角膜が混濁したり、他の赤ちゃんと見た目が違うので、注意深い観察が必要です。
親であれば赤ちゃんの病気はとっても心配です。気になることがあれば早めに眼科でご相談ください。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
老眼 (第14回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−「遠視」 さらに疲れやすく− |
|
|
|
老眼は誰もが避けて通れない、加齢現象の一つです。
物を見るには目の中の水晶体というレンズが厚くなったり、薄くなったりして、ピントを合わせます。年をとるとこの水晶体は固くなってしまうので、
ピント合わせができなくなります。
子供のころの水晶体は柔らかくて弾性に富み、カメラのオートフォーカスと同じでどんなに近くのものでもピントを合わせることができます。
ところが、四十歳をすぎると、水晶体が固くなってピントを合わせづらくなり、六十歳になると近くを見ることがほとんど、できなくなってしまいます。
もともと近視の人は、年をとっても近くが見やすくなっています。近視なので眼鏡を外せば、小さな字でも、近づけば読むことができます。
遠視の人は近くも遠くも、よく見える、と思われがちですが、近くだけでなく遠くを見るときも、水晶体と周囲の毛様体という筋肉が頑張ってピントを合わせています。
いつも毛様体が働いているので、目が疲れやすいわけです。なので、遠視の人に老眼が始まると、さらに目が疲れやすくなります。
老眼の症状は近くが見えないだけでなく、目が疲れる、肩が凝る、目がしょぼしょぼするなど、さまざまです。解決策は近くにピントが合う眼鏡(老眼鏡)を掛けることです。
眼鏡は基本的に一定の距離しかピントが合いません。老眼鏡といってもパソコンや新聞、細かい辞書の字など必要とする度の強さは、それぞれ異なります。
近くだけ、近くと遠くの両方、あるいはその中間など、自分の必要とする距離に合わせた眼鏡を使うことが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|
|
|
|
|
網膜剥離 (最終回) 〜目からウロコ・目の病気〜 |
|
−高齢者では急速に進行− |
|
|
|
網膜剥離(はくり)は文字通り網膜がはがれた状態を言います。では、一体どのようにして起きるのでしょう。
四十五歳の男性が「片方の目が下の方から暗くなってよく見えない」と受診しました。
目の中にある網膜は、ものを見るための大事な組織です。網膜には視細胞という光を感じる細胞があり、
網膜の外側にある色素上皮細胞から栄養をもらっています。網膜剥離になると視細胞が色素上皮細胞から離れてしまい、栄養が行き渡らなくなります。
網膜の内側にはゼリーのような硝子体が詰まっています。年齢が上がると、硝子体は溶けて水のようになります。
硝子体の一部が網膜に癒着していると、硝子体に網膜が引っ張られ、裂け目や穴ができることがあります。ここから網膜の下に水が入り込むと裂孔原性網膜剥離になります。
若い人ではゆっくりと、高齢者では急激に網膜剥離は進行します。剥離が広がるにつれて暗く見えづらい部分が大きくなり、中心の黄斑部がはがれると、視力が下がってしまいます。
受診した男性は網膜に裂孔があり、急速に網膜剥離が進行して見えなくなってしまいました。
網膜がはがれても、すぐに治療を行うと治すことができます。狭い範囲の網膜剥離であれば外来通院のレーザー治療で進行を抑えます。
大きな剥離は入院して手術治療が必要です。網膜剥離が長期間続くと、網膜が元に戻っても視力は戻りません。早期に治療することが重要です。
網膜剥離には糖尿病網膜症などで増殖組織が形成され、網膜が引っ張られてはがれるけん引性網膜剥離、
ぶどう膜炎などの炎症で網膜の下に水がたまってはがれる漿液性網膜剥離があります。網膜剥離の種類や進行の程度によって治療方法も異なります。
網膜剥離は片方の目に起きることが多く、両目で見るとなかなか気づきません。普段から片方の目で見て、異常がないかチェックすることが大切です。 |
|
|
|
▲このページの TOP へ |
|